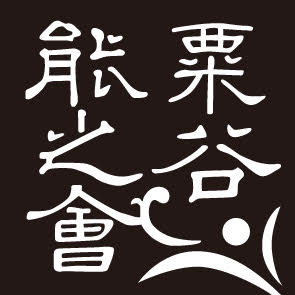我流33 『葛城』 『望月』
我流『年来稽古条々』( 33 ) ―研究公演以降・その十一― 『葛城』 『望月』について
明生 今回も次の粟谷能の会(十月十三日)で勤める曲について話していきましょう。私が『葛城』を小書「神楽」で、能夫さんが『望月』を勤めることになっています。まずは『葛城』から。私は平成六年春の粟谷能の会で『葛城』を、「神楽」の小書で勤めています。古式の神楽がある事を知り、囃子方は小鼓が幸流、大鼓が葛野流、太鼓が金春流、笛は森田流の組み合わせに限ることもあって、太鼓は金春惣右衛門先生、笛は中谷明先生、小鼓は亀井俊一氏、大鼓は若手の亀井広忠氏に依頼し、実現出来ました。
能夫 そうだったね。神楽の後の舞は伝書の通り序之舞の位でやったね。小書「神楽」では前段で神楽を舞い、後半ゆっくりな序之舞を舞う。神楽に入る前の「降る雪の」と謡った後も、いろいろ手組が複雑だから長大になる。
明生 そうです。最初の神楽の序はすごく面白く、雪の降り落ちるイメージが湧く雰囲気です。あのとき、観世流の浅井文義さんが観に来てくださって、「いいけれども長過ぎる。再演するときは短くして」って。今回はそのあたりを改善しようと思っています。
能夫 喜多流には「岩戸之舞」という、ちょっとイロエのような小書もあって、僕は平成二十一年十月粟谷能の会で勤めたけれど、これは序之舞自体がなくなってしまう形だね。
明生 他流の「大和舞」という小書も序之舞部分がすっぽりなくなってしまうのもあるようです。「大和舞」といっても各流、各家でいろいろやり方があるようです。
能夫 観世流の「大和舞」を見ると、前シテは陰々滅々にして、雪に閉ざされた大和の国の地に女が佇んでいるという寂寥感がある。あまり舞わず、何か救済を求めているというか、中入り前に焦点があっている。喜多流は面も「増女」をかけるから、やや明るい感じ。謡も張って謡い、舞って表現しようとするところがある。
明生 前シテの装束も、腰巻に水衣と壷折と両用ですね。前回壺折でしたから、今回は水衣にしようかな、と思っています。以前、青山の銕仙会(観世流)の浅井文義さんがなさった『葛城』(大和舞)が印象的で、あの舞台を真似たいと思い、装束を同様にしたら喜多流の方から「紅いろなし無じゃないか!」と言われまして…。
能夫 喜多流の感覚では、後シテは緋色大口が決まりだから赤色が無いと違和感を覚えるのだろうね。でも、あの雪に閉ざされた陰々滅々としたムードを出すには……ねえ。大和舞は白のイメージかも。僕自身、初めて観世流の『葛城』を観たとき、全く別物だと思った。前場がいいな、と思った。雪に閉ざされた深く暗い世界が表現されていて。それにあの神様は特殊。男だか女だかわからない。いろいろなものを背負っているから。‐8‐『葛城神楽』 シテ 粟谷明生 (撮影 三上文規)
明生 そうですね。『葛城』は役の行者という存在が気になります。葛城の女神、明神様が役の行者に言われて葛城山と吉野山の間に橋を架ける工事をする。女神様は顔が醜いから昼間は恥ずかしいと夜しか仕事をしない。それで仕事がはかどらない。役の行者は怒って、女神を呪縛する。神と役の行者の力関係はこの曲では役の行者が上まわる。本来葛城明神は男神なのに、この弱々しい神のイメージから能では女神として創られているということなのでしょうか? 何か不思議ですよね。
能夫 不思議で面白いのね。
明生 屁理屈を承知で、そこに女性の美しさとか閉塞感を表現するのかもしれない。
能夫 歌舞の世界と、人間の世界の妄執をミックスして…。女性のコンプレクスとかいろいろな要素があるよね。神のお話だから、我々の知り得ない域があったりして。
明生 山の中の不思議な世界。大自然のスケール。葛城山一言主への信仰があって…。
能夫 古代的な原風景みたいなものね。面白い曲なんだな。そういうことが分かってきましたよ。『葛城』では忘れられない思い出があって。憧れの寿夫先生と言葉をかわしたときの思い出。「君は今度、何を演るの?」と聞かれて「『葛城』です」と答えると「あれは面白い曲だね。神様の世界を描いているのが面白いね」と仰った。あの頃の僕は、何だか手応えのない面白くない曲としか思っていなかったが、寿夫先生のお言葉ではっと気が付いたんだ。そしていろいろ考えるようになった。その『葛城』を勤めたのは昭和五十五年秋の粟谷兄弟能、兄弟能の最後の会。その次から粟谷能の会に改名をしたからね。そのときは小書なしの普通で。『道成寺』を勤めて、ちょうど一年後のことだったなあ。
明生 私も若いときは『葛城』はさほどよい曲だとは思わなかった…。
能夫 そうだね。『道成寺』の後、もっといい曲をやらせてほしいと思っていたから。「よい曲だよ」と、寿夫先生のお言葉、もう、頭から離れないよ。
明生 それが能夫さんの曲の読み込みや作品の理解、掘り下げをするきっかけとなったわけですね。
能夫 そう。『葛城』だって、背景にはいろいろな説話と伝承があって、表に出てくるのはほんの一部。その後ろの部分を知って演能に活かしたいね。
明生 いろいろな資料を元にして演能出来る環境を作っていきたいですね。そしてそれを書き残し、そうしておけば何年かあとには、こういうことをやっていたと参考になるかもしれない。
能夫 新しいことをするには、いろいろな抵抗、反撥もあるけれど、そこはご無礼にならないように、手続きを踏んでやってきたね。
明生 それが大事です。根拠を示し、自分の思いを伝え、頭を下げて依頼する、この三点セット、この姿勢が大事で、この一つでも欠けると、うまくいかないでしょう。
能夫 以前『三輪』の「岩戸之舞」を演りたく、お囃子方にご出演のお願いしたら「岩戸之舞とはなにか?」と、逆に問われて、そのとき伝書に書いてあった「暗闇の神楽」、このキーワードをお話して納得してもらったわけ。
明生 そういうキーワードは説得力がありますね。では、『望月』に話を移しましょう。能夫さんの披きはいつですか。
能夫 平成六年三月の粟谷能の会。四十四歳のときかな。僕はね、本当は『道成寺』を演って、『望月』も披いてから結婚、と思っていた。この二曲は能を志す人間のいわば卒業試験のようなものだからね。二十八歳ぐらいまでにそれだけの実力をつけ、それだけの人材になって、それから結婚しようと、それが僕の目指すところだった。でも無理だったけれどね(笑)。
明生 結婚は『道成寺』の後でしたね。
能夫 いや、『道成寺』が昭和五十四年で三十歳のとき、結婚はその一、二年前かな。『道成寺』のあと何年かして『望月』をと考えたけれど、なかなか難しかった。
明生 宗家のお許しが出ませんでしたね。
能夫 あのときは菊生叔父が、新太郎の喜多流への貢献などご配慮いただき、それに免じてやらせてくださいとお願いしたが、実現しなかったね。
明生 残念でしたね。能夫さんの先輩たちは、二十代で『道成寺』を披かれていましたから、その後に結婚もあり得たのでしょうが、いつからか、二十代の『道成寺』は早い、という風潮に変わりましたね。ましてや『望月』は獅子舞があるということで重く扱われ、ますます披く時期が遅くなって来ています。
能夫 喜多流で獅子舞があるのは『望月』と『石橋』だけ。どのように二曲を思うかな。
明生 『望月』と『石橋』の獅子舞は別物と考えています。一般に『石橋』を基盤に『望月』はややしっかり囃してなどと言いますが、そういう違いではなく、『望月』の戯曲の中での獅子舞という発想でないといけないと思います。
能夫 確かに『望月』と『石橋』の獅子舞は違うね。『望月』は座敷舞的なもので、その系統のものは、角兵衛獅子とか越後獅子とか、日本中にも多く伝わる芸能だ。それに対して『石橋』は能に代表されるように、特殊なもの。抽象的で観念的、宗教的で聖なる別世界という感じ。当然違ってしかるべきですよ。扮装も全然違うしね。『石橋』は面をかけるけれど、『望月』は直面で、赤頭だけれども覆面をして唐織『望月』 シテ 粟谷能夫 (撮影 あびこ喜久三)をカヅいて出てくるわけですから。
明生 『望月』は、主君の仇討ちをしようとする緊迫した状況で、酒を呑んでいる望月秋長(ワキ)に余興として獅子舞を見せ、油断させて復讐する、その意図が見え隠れしないとつまらない。
能夫 シテ(小沢刑部友房)はすきを見て仇を討とうと狙っている。子方の花若(主君安田友春の子)に本懐を遂げさせようと…。
明生 油断させるための舞ですから、まず第一に見ていて面白くなければいけない。第二に、演者として獅子舞を舞える喜びを内に秘めながら、どう感じ、どう舞うかです。今回、能夫さんはどのように獅子を、『望月』を勤められるのか。演者の気持ちが外に出過ぎるのはいけないでしょうが、あまり内向き過ぎると、作品の面白さが湧いて来ないかも知れない。爆発寸前のような表現があってもいいのでは。うまく言えないのですが…。
能夫 爆発? それはすごいなあ。でもまあ、六十歳過ぎて、失うものはなにもないから…やってみましょうか(笑)。もちろん、内向なんてことはないよ。仇を討つ、人を殺すという緊迫した意識だから。でも、そこを冷静に戻して獅子舞をする、芸能者として演じる、殺せ殺せだけでもない気がするよ。
明生 そうですが…。
能夫 殺気を感じさせながらも、それを押し込める。
明生 そうそう。囃子方にもその精神を理解していただき囃してもらわないといけませんね。ただただ『石橋』をベースにして、段数が一つ減る、位(スピード)を少し落とすぐらい、そのような判断基準ではなく、ひとつの作品を創る意識で囃していただきたい。
能夫 囃子方は普通、段数と位しか聞いてこないね。
明生 そのときに、シテとして今回の獅子は…、どのように考えどう舞うのかをきちっと言いたい、言えなくてはいけないですね。
能夫 それはそう。囃子方とは共通認識が必要だからね。
明生 私が『望月』(平成十二年三月・粟谷能の会)を披いたとき、子方が息子の尚生でした。打上会で能夫さんが注意してくれた言葉は今でも忘れられないんですよ。「望月は言葉だよ。科白劇。獅子を上手にこなすのはもちろんだけれど、言葉の深みを大事に謡ってほしい。たとえば〝本国へも叶わず〟と言うときの息、呼吸」と言いました。本国、つまり自分の国に帰ることもできずに守山の宿で兜屋の亭主として身をやつし、旅人を泊めている。仇討ちの機会を狙っていたが、さて今本当に…という、その境涯を語るのだと。確かに私は、息子と『望月』ができたこと、息子と獅子で満足していました。あの科白劇での謡の息、その大切さを知らされた瞬間でもありました。
能夫 無念さというか。仇討ちをしようとしてかなわず、立派な武士だった人が、身をやつしているわけだよ。挫折感もあるだろうし。そこに、主君の奥さんと子どもがやってくる、次に仇の望月が来る、でき過ぎた場面設定だが、まあ、芝居だからね。この時を逃してはいけない。忍従していた時間があったからこその思いが、謡の言葉から立ち上ってこないといけない。
明生 能夫さん、『望月』は二度目になりますね。
能夫 そう。今は振り返るときだと思っている。
明生 再演には、再構築もありますが、単に塗り直し程度もあるでしょう。
能夫 さて、どちらかな…。やはり自分なりに積み重ねてきたものを再度舞台でやりたいという欲望かな。
明生 我々は新しいことに挑戦していますが、それはいつも後ろを振り返り、もう一回前を向いて少しずつ進むというやり方をしていると思います。そこには周りからの忠告やヒントになる言葉もよい投薬になっていますね。つくづくと、刺激と積み重ねの重要性を感じています。
能夫 振り返りながら少しずつ前進しようね。 (つづく)
写真 『葛城神楽』 シテ 粟谷明生 (撮影 三上文規)
『望月』 シテ 粟谷能夫 (撮影 あびこ喜久三)